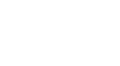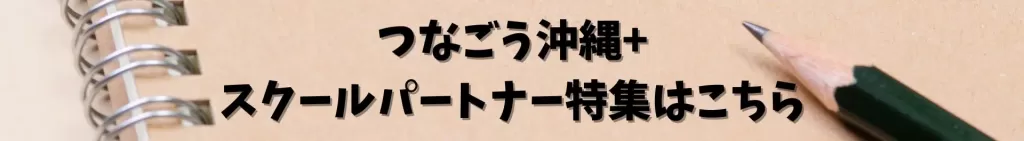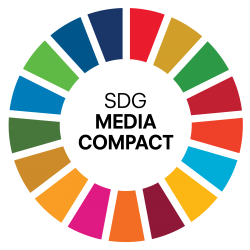澄みわたる大空とまばゆい海
島々で育まれた文化や歴史は、
私たちが暮らす沖縄の宝。
私たちは、
ふるさとの宝を未来へつなぐため
積極的に発信し、地域と連携し、
自ら行動します。

SDGsはとても大きなテーマですが、
行動は身近なところから。
しっかりと足元の課題を見つめ
世界とつながりながら
子どもたちの笑顔とこの島の自然
持続可能な発展が共存する
平和な社会の実現に取り組みます。
テレビ・ラジオ・イベントなどを通して
SDGsに関する情報を発信し、課題解決へともに考えます。

パートナーシップは活動の原動力。
県民・企業・団体と手を取り合って着実に前進します。
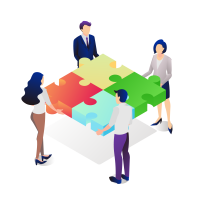
まずは私たちから。
率先して行動し取り組みの輪を広げます。



RBCはSDGsの取り組みを推進するため、
国連の「SDGメディア・コンパクト」に
2021年5月17日に加盟しました。
「SDGメディアコンパクト」は国内外約150の
報道機関等が登録しており、
県内マスコミではRBCが
初めての加盟となります。

琉球放送は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
参照:国際連合広報センター
SDGsとは、“Sustainable Development Goals”の略で「持続可能な開発目標」と訳されるものです。 2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、国際社会が2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットが掲げられています。

×